法定後見と任意後見の違い

『法定後見制度』は法律の規定によるもので、 認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が無かったり、不十分な状況に陥っている方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように法律面や生活面で支援するため、家庭裁判... 続きを読む


『法定後見制度』は法律の規定によるもので、 認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が無かったり、不十分な状況に陥っている方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように法律面や生活面で支援するため、家庭裁判... 続きを読む

成年後見人(保佐人・補助人)の業務は、原則として有償です。 これは、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職が後見人等である場合に限らず、ご本人の家族が後見人等である場合も同様です。 なので、親族後見人であっても報酬をもらうことは可能です。 &n... 続きを読む

法定後見(保佐・補助)を利用するには、申立人が家庭裁判所に後見開始等の審判の申立てを行う必要があります。 後見開始等の申立人は法律で定められています。 家庭裁判所に後見等開始の申立てをすることができる人(申立人)は、法律で次のように... 続きを読む

成年後見人になるには、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所に選任される必要があります。 認知症の人がいることを知った家庭裁判所が自ら後見を開始してくれるわけではなく、必ず関係者が家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てを行わなければな... 続きを読む

後見監督人とは、後見人の事務を監督する者ですが、後見や保佐、補助が開始すれば、必ず監督人も選任されるというわけではなく、家庭裁判所が「必要があると認めるとき」に監督人は選任されます。 ※ご本人や親族、成年後見人から監督人選任の請求があった場合にも... 続きを読む

後見開始の審判を申立てるには、まずは必要書類等の準備をするところから始まります。 必要な書類や費用は次の通りですが、裁判所によっては必要となる書類等が異なりますので、もしもわからない場合は、申し立て先の家庭裁判所に直接尋ねると良いですね。 &nb... 続きを読む
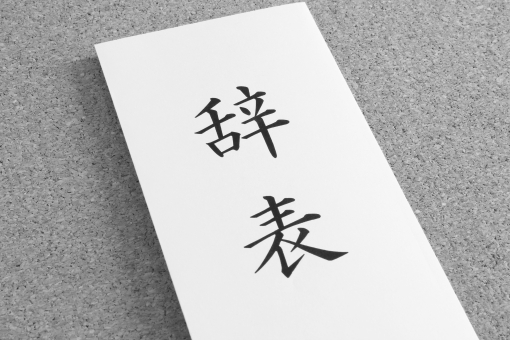
「祖父が亡くなり、母が相続人の一人になっているのだが、母は認知症のため、後見人を就けないと相続手続きが進められない(遺産分割協議ができない)と知人から聞いた。母のために司法書士に後見人になってもらい、相続手続きが終わった時点で、後見人を辞めても... 続きを読む

成年後見(保佐・補助)は、一度申立てをすると簡単には取下げができません。 以前は成年後見等の申立てを自由に取下げることが可能でしたが、今は、後見開始等の申立てを取下げるには、裁判所の許可が必要になりました。 どんなときに家庭裁判所は後見申立ての取... 続きを読む
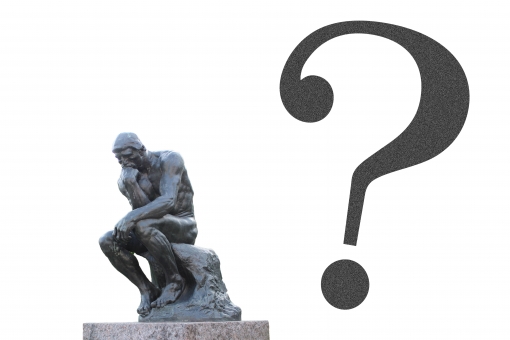
法定後見(成年後見・保佐・補助)を利用するには、申立書等を作成し、資料を揃えて申家庭裁判所に申立てる必要があります。 申立書にはご本人の判断能力に応じ、「後見開始・保佐開始・補助開始」何れかの内容を記載しなければならないのですが、ご本人の状態が後... 続きを読む

財産目録とは、 不動産、預貯金、現金、有価証券(株式・投資信託等)、生命保険などの『資産』と、 借入金や未払金などの『負債』を、わかりやすいように一覧にしたものです。 後見人(保佐人・補助人)は、財産目録を作成し、就任してから原則として1ヶ月以内... 続きを読む