どうすれば認知症の母の財産を管理できるの? 成年後見人になるには? ~後見等開始の審判がなされるまでの流れ~

成年後見人になるには、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所に選任される必要があります。 認知症の人がいることを知った家庭裁判所が自ら後見を開始してくれるわけではなく、必ず関係者が家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てを行わなければな... 続きを読む


成年後見人になるには、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所に選任される必要があります。 認知症の人がいることを知った家庭裁判所が自ら後見を開始してくれるわけではなく、必ず関係者が家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てを行わなければな... 続きを読む

後見監督人とは、後見人の事務を監督する者ですが、後見や保佐、補助が開始すれば、必ず監督人も選任されるというわけではなく、家庭裁判所が「必要があると認めるとき」に監督人は選任されます。 ※ご本人や親族、成年後見人から監督人選任の請求があった場合にも... 続きを読む

財産目録を作成する前提として、まずはご本人の通帳や不動産権利証などを、それらを管理している人から引渡しを受ける必要があります。 ご本人(成年被後見人)が管理している場合はご本人から、親族が管理している場合は親族から引継ぐことになります。 紛失等に... 続きを読む

家庭裁判所は、成年後見人・保佐人・補助人に不正な行為、著しい不行跡、そのほか法定後見の任務に適しない事由があった場合、本人やその親族、後見監督人、検察官からの申立て、または職権によって解任することができます。 不正な行為 本人の財産を横領したり... 続きを読む

後見制度支援信託とは、ご本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を後見人が管理し、通常使用しない金銭は信託銀行に信託する仕組みをいいます。 後見制度支援信託が設定されると、信託された財産を払い戻したり解約したりするためには、家庭裁... 続きを読む

任意後見監督人は主に、 任意後見人の事務を監督して家庭裁判所に定期的に報告すること。 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をすること。 任意後見人またはその代表する者(任意後見人の親権に服する未成年者や、任意後見... 続きを読む

・ 相続が開始し、成年後見人と被後見人がいずれも相続人である場合(例えば、親子ともに相続人である場合)において、遺産分割協議を行う場合。 後見人と被後見人がいずれも相続人である場合で、被後見人が相続放棄をする場合。 成年後見人が個人的に金融機関から借入れを行... 続きを読む
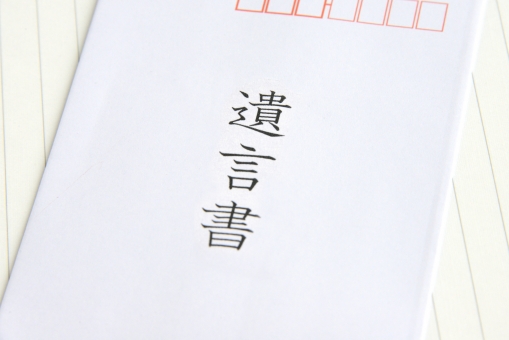
遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後、その意思を実現させる為に制度化されたものです。 そして、成年被後見人も遺言を作成することは可能で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも作成が可能です。 但し、... 続きを読む

後見制度支援信託は、ご本人が日常生活で使用する分を除き、全額信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。 これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、その都度、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人が勝手に... 続きを読む

後見制度支援預金とは、ご本人の財産である預貯金を、日常的な支払いをするための金銭(これは後見人が管理)と、日常的に使用しない金銭とに分け、後者を後見制度支援預金口座に預ける仕組みです。 後見制度支援預金は、通常の預金とは異なり、口座の開設や出入金... 続きを読む